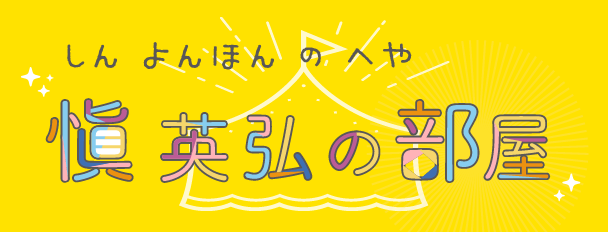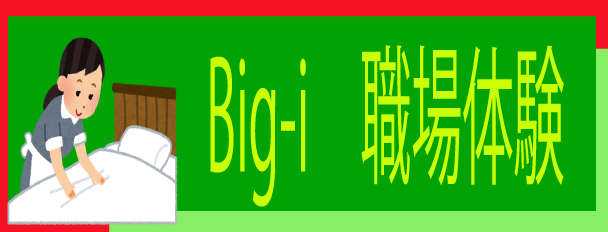国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)
国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。
News
お知らせ
愼英弘の部屋VOL.15「視覚障害者ガイドヘルパー制度」
2025.10.23
愼英弘の部屋
障害者の中には一人で外出することが困難な者がいる。そのような人のために、外出を支援する制度として“ガイドヘルパー派遣制度”がある。この制度の実施によって、障害者の日常生活の充実や社会参加が促進されていることは多言を要しない。
ガイドヘルプサービスを利用する障害者にとっては、ガイドヘルパーとの信頼関係が密になればなるほど、より良い日常生活や社会生活を営むことができる。換言すれば、より良いサービスを障害者に提供するためには、ガイドヘルパーの資質の向上が必要である。
今回は、視覚障害者に対して外出支援をするガイドヘルパーすなわち視覚障害者ガイドヘルパー制度の有用性や課題、ガイドヘルパーの心構え等について述べることにする。
「視覚障害者ガイドヘルパー制度」
1.視覚障害者ガイドヘルパー制度の変遷
視覚障害者とりわけ全盲の者にとって、外出時に白杖1本を頼りに一人で自らの力で安全を確保しながら道を歩くことは、筆舌に尽くしがたい苦労がある。道の両側には溝があったり、至る所に自転車や看板が置いてあったり、店の前には商品を載せた台が出ていたり、視覚障害者にとっては歩行を妨げる障害物といえるものがあるからである。
晴眼者(目の見える人のこと)にとっては、これらの障害物があったとしても、歩行時に筆舌に尽くしがたいような苦労はないはずである。なぜなら、晴眼者は視覚を通して周辺状況を把握することができるので、これらの障害物を避けながら歩くことができるからである。
視覚障害者、中でも全盲の者は、視覚を通しての周辺状況を把握することが困難であるため、常に安全を確保できるという状況とは限らない。
したがって、視覚障害者が一人での外出時に安全を確保するために、晴眼者の手助けがあるならば、安心して外出できる。
視覚障害者の外出時における支援は、ボランティア活動から行政施策へと発展していった。誤解を避けるために一言しておくが、行政施策としてのガイドヘルパー制度が実現したからといって、ボランティア活動としての支援が廃れたわけではない。
視覚障害者に対する外出支援の変遷は、次の7段階があるといえる。
(1)個人としてのボランティア活動
近隣に視覚障害者が住んでいたり、友人に視覚障害者がいたりすると、その視覚障害者が外出しようとするときに、近隣の者や友人たちはボランティアとして外出に付き添うことがある。このような状況は、無理矢理に押しつけられてするものでもなく、だれかから言われてするわけでもなく、その人がもちあわせているボランティア精神の現れであるといえる。
ボランティア精神の現れとしての支援活動は、知り合いの人だからするだけではなく、まったく見知らぬ人に対しても、その人が困っているような状況におかれていると感じたときには支援の手を差し伸べる人がいることは、枚挙に遑がないほど見受けられる。
個人としてのボランティア活動の支援は、視覚障害者ガイドヘルパー制度が行政施策として実施されている今日においても、廃れることなく、なされている。全盲の私はほぼ毎日のように一人で外出しているが、至る所で、見知らぬ人から声をかけられ、外出時に手助けをしてもらっている。道路を横断しようとするときに信号の色が赤であるか青であるかを教えてくれたり、一緒に道路を渡ってくれたり、自転車や看板が置かれているような道では手引きをしてくれたり、本当に心温まる手助けをしてくれる人がたくさんいる。
(2)ボランティアとしての手引きの会
視覚障害者にとっては、外出時に個人的にボランティアとして支援してくれる人がいることはたいへん助かる。しかし、一人で外出しているときに、必ず支援してくれるボランティアに出会うとは限らない。したがって、視覚障害者にとっては、外出を支援してくれるボランティア組織ができることが待たれていた。
民間人の中に、視覚障害者の外出を支援するためのボランティア活動を組織的にしようとする状況が生まれるようになった。そして、視覚障害者の外出を支援するための“手引きの会”が結成されるようになった。
現在では行政施策による外出支援制度ができているが、それとは別に、ボランティア精神に裏打ちされたボランティア活動としての手引きの会が各地に存在している。ボランティア活動であるので、ガイドヘルパーは手当の支給を目的にしないし、利用者である視覚障害者は基本的には利用料を負担することはない。
私は手引きの会の支援を一度も受けたことがないので、具体的な利用実態については知らない。何ゆえに利用したことがないかの理由は、単に利用の機会がなかったからである。
(3)盲人ガイドヘルパー制度
民間人による視覚障害者の外出支援のための手引きの会とは別に、都道府県や政令市等にある視覚障害者団体(名称は盲人協会や視覚障害者福祉協会等さまざまである)によって、“盲人ガイドヘルパー派遣事業”が展開されるようになった。
1974(昭和49)年度には、身体障害者福祉法における地域活動促進のメニュー事業として“盲人ガイドヘルパー派遣事業”が追加され、国の予算による事業として位置づけられた。視覚障害者が外出する際の付き添い者が公的に派遣されることが制度化された。とはいえ、メニュー事業であるため、すべての自治体が実施するとは限らなかった。
都道府県・政令市の“障害者社会参加促進事業”に位置づけられていた“盲人ガイドヘルパー派遣事業”は、1967(昭和42)年から制度化されていた“身体障害者家庭奉仕員派遣事業”と1988(昭和63)年度の予算から一緒になり、市町村の実施事業に移行された。
この制度では、利用者には利用料の負担が導入されたが、さまざまな大会や行事、余暇活動への参加にもガイドヘルパーの利用ができるようになるなど、公的制度としてのガイドヘルパー派遣が広がっていった。
(4)視覚障害者ガイドヘルパー制度
「盲人」という言葉は差別語でもなく、蔑んだ名称でもないが、当事者の間でもその呼び方を避ける傾向が広がっていった。そして、“盲人ガイドヘルパー”は“視覚障害者ガイドヘルパー”と呼ばれるようになっていった。
大阪市においては、1997(平成9)年4月から、視覚障害者の外出を支援する事業を制度化するために、同年1月17日からガイドヘルパーの養成研修を実施した。受講者の多くは、それまで“盲人ガイドヘルパー”としてボランティア活動をしていた人であった。
そして、研修の終了後に、同年4月から大阪市による“視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業”が開始されると、そのガイドヘルパーとして活動するようになった。それはボランティアとしてではなく、活動に対して手当が支給されるガイドヘルパーとしての活動であった。
(5)移動介護制度
2003(平成15)年4月から障害者福祉サービスの体系が大きく変わった。それは、“支援費制度”の導入による。この制度は、利用者と福祉サービス提供者との対等な関係を樹立するために、受けたサービスの利用料を利用者が福祉サービスの提供者に支払うというものであった。しかし、現実には、行政から利用者に福祉サービスの利用料を直接渡すのではなく、福祉サービスの提供者に代理受領させる仕組みであった。したがって、当初の目的の一つであった対等な関係の樹立は狙い通りにはなりようがなかった。
支援費制度では、福祉サービスのすべてではないが、それまでの“措置制度”から“契約制度”に変わった。視覚障害者ガイドヘルパー派遣制度は“移動介護制度”と位置づけられ、同制度も、利用者である視覚障害者が、サービス提供者である事業者と自由に契約できる制度になった。このことによって、対等な関係となっていった。
しかし、この支援費制度は、長く続かないことが最初から明らかな制度であった。そのことは拙著『自立を混乱させるのは誰か』で指摘した通りである。
長く続かないことが最初から明らかであった支援費制度ではあるが、移動介護制度としての視覚障害者ガイドヘルパー制度の利用における契約制度は、支援費制度が崩壊した後も現在まで続いている。
(6)移動支援制度
支援費制度はわずか3年で崩壊し、2006(平成18)年4月から“障害者自立支援法”による福祉体系に移行した。
同法の下では、移動介護制度は“移動支援制度”と改められた。すなわち、視覚障害者ガイドヘルパー制度は移動支援制度として、市町村の必須事業となった。
盲人ガイドヘルパー制度も、視覚障害者ガイドヘルパー制度も、移動介護制度も、移動支援制度も、提供されるサービス内容はほぼ同じものである。すなわち、共通しているサービス内容は、視覚障害者の外出時に安全を確保しながら目的地まで行き、最終地まで送り届けるためのガイドヘルパーを派遣するというものである。若干異なるものとしては、視覚障害者に対して情報提供等をサービスに位置づけている制度がある。
(7)同行援護制度
視覚障害者が外出時に安全を確保されることはもっとも重要である。しかし、外出には目的がある。目的があるからには、その目的が達成されるための外出にならなければならない。換言すれば、視覚障害者へのガイドヘルパーの派遣は、利用者である視覚障害者の外出目的を達成できるものでなければならない。単に、安全を確保さえすればいいというものではない。
視覚障害者の外出目的にはさまざまなものがある。役所への書類の提出、銀行での出金、会議に参加、講演を聴きに行く等々。ガイドヘルパーに安全を確保してもらいながら外出ができたとしても、これらの目的が達成されなければ、何のための外出なのか意味をなさない。
したがって、視覚障害者にとっては、外出時の情報提供や書類の代読・代筆は欠かすことができない重要問題である。移動支援の中でも情報提供はなされていたが、代読や代筆はサービスとして提供されることはなかった。
銀行に出かけて自分の預金から出金しようとしても、出金の書類に書くことができなかったら、自分のお金であっても出金してもらえない。かつては銀行職員が代筆することはなかった。同行しているガイドヘルパーが代筆をしてくれれば出金できるが、ガイドヘルパーが代筆を拒否すれば出金ができない。代読や代筆はガイドヘルパーの仕事としては制度化されていなかったので、強制的に代筆させることはできない。
したがって、視覚障害者にとっては、外出時に代読や代筆をするサービスが移動支援制度に位置づけられることが望まれていた。そのための運動も行われていた。
運動の結果、2010(平成22)年12月に障害者自立支援法の一部が改正され、視覚障害者に対する移動支援のサービス内容に、代読・代筆や身体介護が盛り込まれた。
改正障害者自立支援法における視覚障害者に対する移動支援は、“同行援護制度”として位置づけられ、それは翌年すなわち2011(平成23)年10月から全面施行された。これによって、視覚障害者は外出時に、“同行援護従業者”すなわちガイドヘルパーによって、外出時の安全が確保されるのみならず、目的地での代読や代筆による書類の作成、情報提供による必要な情報の入手、身体介護が必要な場合には介護サービスを受けることができるようになったのである。
この同行援護制度は、障害者自立支援法が改正後の2013(平成25)年4月からの“障害者総合支援法”によって現在まで引き継がれている。
とはいえ、同行援護制度は充分なサービスが提供されているとは限らない。なぜなら、必要なサービスの量が認められているからではない。原則として1カ月に利用できる時間数が制限されているからである。それだけではない。居住している自治体によって格差がありすぎるのである。たとえば、大阪市に居住している視覚障害者が利用できる同行援護の時間数は1カ月に原則51時間であるのに対し、隣の自治体である東大阪市に居住する視覚障害者は1カ月に原則80時間も利用できるのである。利用時間数の制限や、自治体におけるこのような格差を、いかにして解決するかは大きな課題である。
2.ガイドヘルパーの心得
同行援護従業者(以下、ガイドヘルパーという)の資格は、一般課程では3日、応用課程ではその3日に加えて1日の養成研修を受けさえすれば取得できる。資格取得における試験制度はない。したがって、研修さえ受講すれば、おそらくは問題なく資格を取得できるのである。ここで「おそらくは」と記したことについては最後の節で述べる。
しかし、資格を取得しただけでは、良きガイドヘルパーになれるとは限らない。良きガイドヘルパーになるためには、障害者、特に視覚障害者に関係することについての学習を怠らないことであり、後述する“ガイドヘルパーの心得10箇条”を肝に銘じて活動することである。
(1)学習を怠ってはならない
視覚障害者関係についての学習としては、少なくとも次のようなことについて知識を深めることである。
ア.点字ブロック
点字ブロックは視覚障害者が単独歩行するときに、安全を確保するための手がかりになる。しかし、点字ブロックには長所もあれば短所もある。このことは今回は詳述しない。
点字ブロックは至る所に敷設されているので、ほとんどの人は見たり踏んだりしているだろう。したがって、ここでは詳しい説明は割愛する。視覚障害者の手引きをしているときに、ガイドヘルパーとして点字ブロックの使い方をどうすればいいのかについてだけ述べることにする。
-
-
-
- 手引きをしているときに地面や床に点字ブロックがあることを視覚障害者に伝える。
- その点字ブロックの上を歩きたいかどうかを視覚障害者に尋ねる。
- その希望に応じる。
- 特に希望する返事がないときには、点字ブロックの上を歩かず、点字ブロックに沿って歩くようにする。点字ブロックの上を歩くと滑ったりつまずいたりすることがあるからである。
- 点字ブロックに沿って歩くのは、歩いている方向を視覚障害者が認識できるようにするためである。その知識は、視覚障害者が単独で同じ場所を歩くときに役立つからである。
-
-
イ.音響式信号機や触知式信号機
音響式信号機や触知式信号機には長所もあれば短所もある。このことについて、今回は詳述しない。
音響式信号機とは、信号の色が青になると、それを知らせるための音が鳴る信号機のことである。触知式信号機とは、信号の色が青になると、信号機のポールが振動して知らせる信号機である。ポールに触れることによって、青であることが確認できるのである。
音響式信号機が設置されていることは、その音によって、視覚障害者も認識できる。しかし、触知式信号機は、単にポールが振動するだけであり、音響式信号機のように音がしないので、それが設置されているかどうか視覚障害者は認識できない。
したがって、視覚障害者をガイドしながら道を歩いているときに、触知式信号機が設置してあることに気づいたガイドヘルパーは、必ず視覚障害者にその情報を伝える必要がある。なぜなら、単独歩行する視覚障害者もいるので、触知式信号機の設置の情報は道路を安全に渡るための重要な手がかりになるからである。
ウ.障害者の心理
視覚障害者についての心理学を学べと言っているのではない。ガイドヘルパーと共に移動している視覚障害者の心理状態について認識してもらいたいのである。
私は大阪市の生野区で17年間にわたって、どんな相談にも応じるというボランティア活動をしていた。あるとき、視覚障害者からの相談があった。それは、ガイドヘルパーと一緒に移動しているときに、その人が「怒鳴る」というのである。何か質問をするとすぐに大声を出して「怒鳴る」とのことである。どうしたらいいかとの相談であった。私は「ガイドヘルパーを他の人に変えてはどうか?」と言ったら、「その人はよく怒鳴るけど親切なんです」と言う。「親切だけど、怒鳴られると、とてもストレスが溜まるんです」と嘆いていた。
視覚障害者はガイドヘルパーに対して、一面ではたいへん感謝をしているが、他の一面では、ガイドヘルパーの態度次第でストレスが溜まるほど悩む状態になることがある。このことをガイドヘルパーは充分に認識すべきである。資格取得のための養成研修では、必ず人権についての講義がなされている。その中でヘルパーの支援とストレスに関する内容も触れられているはずである。ガイドヘルパーは養成研修を受講したときの内容をときどきは振り返るべきである。
エ.障害者の生活状況
同じような視覚障害があったとしても、人によって生活状況はいろいろである。外出をあまりしたがらない人、可能な限り外出をする人。視覚障害者も多数集まれば「十人十色」である。
したがって、視覚障害者の生活状況を固定観念で捉えないことが肝要である。ガイドヘルパーは、支援をする視覚障害者を「十把一絡げ」に捉えるのではなく、一人一人の話を充分に聴き、あるいはコミュニケーションを密にして、その人のニーズや生活状況を把握する努力が必要である。そうしないと、視覚障害者が満足する手引きや情報提供ができにくいかもしれない。
(2)利用者は消費者
視覚障害者に対するガイドヘルプサービスの提供を、「してあげている」などという立場でしてはならない。視覚障害者は同行援護というサービスの利用者であることを、ガイドヘルパーは認識しなければならない。こんなことを書くと、ガイドヘルパーの多くは「わかりきっていることだ」と言うかもしれない。本当に「わかりきっている」だろうか。「サービスの利用者」を「サービスの消費者」と置き換えたら本当に「わかりきっている」と胸を張って言えるだろうか。
ガイドヘルパーは同行援護という福祉サービスを提供し、視覚障害者はそのサービスを利用して外出をするのである。その意味では視覚障害者はサービスの利用者である。違う側面から考えてみると、ガイドヘルパーは、自らの身に付けている知識や技術を同行援護という「商品」として、視覚障害者にお金と引き換えに売っているのである。換言すれば、視覚障害者は、ガイドヘルパーから同行援護という商品を、消費者としてお金を出して購入しているのである。したがって、視覚障害者はガイドヘルパーの提供するサービスの利用者であり、別の言い方をすると、視覚障害者はガイドヘルパーが商品として売る同行援護サービスを購入する消費者なのである。
サービス=商品の提供者であるガイドヘルパーは、利用者=消費者である視覚障害者が満足するサービス=商品を提供するのが、市場経済のあり方である。ガイドヘルパーはいいサービス=商品を、視覚障害者に利用=購入してほしければ、自らの知識を深め技術を向上させる必要があることは多言を要しない。
(3)ガイドヘルパーの心得10箇条
サービスを受ける側から見たとき、望ましいガイドヘルパー像とは、次のようなことを心がける人である。すなわち、より良いガイドヘルパーになるための“ガイドヘルパーの心得10箇条”。この10箇条は、ガイドヘルパー制度において確立され義務づけられたものではなく、私が考えているガイドヘルパー像である。
この10箇条を守らなくてもガイドヘルパーはできる。しかし、そんな人は、良いガイドヘルパーになることは難しい。利用者である視覚障害者から信頼されるガイドヘルパーになるには、この10箇条を守り、常に念頭において活動することが肝要である。
ア.秘密を守ること
ガイドヘルパーの養成研修では、ガイドヘルパーには守秘義務があることを講義で学んでいるはずである。
したがって、ガイドヘルパーをしているほとんどの人は、「仕事上知り得た利用者の秘密を守るのは当たり前だし、他人に洩らしたことはない」と言うだろう。本当に秘密を守っているだろうか。知り得た秘密を他人に洩らしていないだろうか。
私はいろんな人からよく耳にすることがある。それは、利用者がガイドヘルパーの同行援護で外出したとき、二人の間で交わした話の内容や、他の人の噂話の内容が、明くる日には広まっている、と。利用者には守秘義務が課せられてはいないとはいえ、利用者もガイドヘルパーも、とにかくよくしゃべる。ここには書きがたいような内容をガイドヘルパーがしゃべり回っているひどい状況もある。
私は同行援護を利用するとき、口の堅いガイドヘルパーに依頼している。私の行動を話されて困るようなことはないが、噂話のネタにされたくないからである。
ガイドヘルパーは守秘義務について、念には念を入れて守るべきである。正当な理由がない限り、秘密を洩らしてはならない。どうしても話さなければならないような問題が生じたならば、利用者や他のガイドヘルパーに話すのではなく、ガイドヘルパーを派遣している事業所の管理者やコーディネーターに相談すべきである。
イ.利用者のニーズを尊重した活動をすること
ガイド中に利用者とガイドヘルパーとの間で手引きの仕方に関して意見の相違があったときには、安全確保をもっとも重要視した手引きをしなければならないのは多言を要しない。安全確保とは関わりのないことで意見が異なった場合には、利用者のニーズを尊重するように心がけるべきである。たとえば、どの道を通って目的のところに行くか、交通機関は何にするかなどは、安全確保上問題がないならば、利用者のニーズを満足させるべきである。
視覚障害者には情報提供が重要であるからといって、必要以上の誘いはやめるべきである。視覚障害者の外出の機会を増やしてあげるつもりで、いろいろな行事等の情報を提供するガイドヘルパーがいる。情報を提供することは良いことだが、無理矢理に外出を誘ってはならない。なぜなら、利用者は「ガイドヘルパーがせっかく情報をくれて、参加を誘ってくれているので、断っては関係が悪くなるかもしれない」などと気遣うことがあり、行きたくもない行事やイベントに嫌々行くことがあるかもしれないからである。
ウ.約束は守ること
これも当たり前のことであり、ことさらにいう必要はないだろう。しかし、一言しておく。
午前10時に利用者宅までガイドヘルパーが迎えに行く約束をしているにもかかわらず、5分が過ぎてもヘルパーが来なかったら利用者である視覚障害者は非常に不安になる。「来ないのだろうか」「約束を忘れているのだろうか」「来る途中で事故にあったのではないだろうか」等々。約束の時刻にたどり着けないのであれば、必ず連絡すべきである。
「5分遅れてすみません。遅れた分は延長してガイドします」というガイドヘルパーがいたとしたら問題である。帳尻を合わせれば、それでいいというものではない。その5分間の遅れの間の視覚障害者の精神的不安やストレスは筆舌に尽くしがたいものである。ガイドヘルパーは約束した時刻の5分前には迎えの場所に到着するように心がけるべきである。
エ.自分の生活の中にガイドヘルプ活動を位置づけ、長く続けること
長く続けているガイドヘルパーは、さまざまな経験を積んでおり、多くの利用者と関わっているはずなので、知識も技術も豊富だと考えられる。そのようなガイドヘルパーに対しては利用者は高い信頼を寄せるだろう。学習もせず、技術を磨く努力もしないガイドヘルパーがいるかもしれないが、そんな人は論外である。
ガイドヘルパーを長く続けている人は、ガイドすることが自分の生活の一部になっているのかもしれない。そのようなガイドヘルパーになることを期待している。
オ.絶えず学習し自分を高めること
ガイドヘルパーの仕事に慣れ切ってしまうと、「自分はベテランである」との自負をもっている人がいるかもしれない。自負をもつのは決して悪いことではない。しかし、自負は往々にして学習する態度を阻害しかねないことがある。そのようなことにならないためにも、自分の現在の状況に満足するのではなく、絶えず学習をして自分を高める努力が必要である。
カ.謙虚であること
ガイドヘルパーの資格を取得する前の多くの人は、「自分にできるだろうか」「一生懸命勉強してがんばろう」等々ときわめて謙虚な姿勢をもっていたはずである。ところが、ガイドヘルパーとして支援を5年も10年も続けているうちに、その謙虚さが薄れていく人がいるかもしれない。謙虚さの薄れは、ときには傲慢な姿勢になるかもしれない。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という表現がある。稲穂は実がたくさん付いたり実が大きくなったりすると、自然に頭を下げるようになってくる。つまり、人も、知識や経験が豊富になればなるほど、傲慢になるのではなく、稲穂のように頭を下げるような謙虚さをもってもらいたい。
謙虚さがなくなれば、学習の努力を怠るかもしれないし、技術を磨く努力をしなくなるかもしれない。そのようなことになれば、ガイドヘルプの利用者である視覚障害者に、満足してもらえるような支援ができなくなるかもしれないので残念である。
キ.見返りを求めないこと
ガイドヘルパーの活動をしていたら表彰されるのではないかとか、勲章をもらえるのではないかなどの見返りを求めてはならない。なぜなら、見返りを期待しての活動をすると、人が見ているところでは一生懸命に丁寧に支援をするが、見ていないところでは手抜きをするかもしれないからである。表彰や勲章は活動の結果として贈呈されるものであり、最初から見返りを求めるための活動をすべきではない。
ガイドヘルパーとして外出したときに、昼や夜の食事時を挟んでの場合、その食事の費用を利用者が出してくれるのではないかなどの見返りを求めてはならない。その理由は前述したものと同様である。すなわち、食事代を出してくれそうな利用者には親切にするが、出してくれそうもない利用者にはその親切心が欠けるかもしれないからである。
念のために強調しておくが、食堂に入ったとき、その費用を利用者の負担にしてはならない。ただし、事前に話し合って決めている場合は別であるが。
ク.活動の中身を自分の問題として捉えること
同行援護としてガイドヘルパーが支援するときの活動は仕事である。しかし、単なる仕事と考えないでもらいたい。
人は誰でも病気になったり、事故に遭遇したりすると障害者になることがある。また、長生きをすれば、介護が必要な障害状態になるかもしれない。すなわち、現在は健常者であったとしても、将来において障害者になるかもしれないのである。
仕事としてガイドヘルパーをしているとしても、自分もいずれは支援を受ける側になるかもしれないので、ガイドヘルパーの仕事を自分の問題でもあると捉えてもらいたいのである。
ケ.ガイドヘルプ活動は社会活動であるとの認識をもつこと
ガイドヘルパーの仕事は、視覚障害者個人に対する支援であることはいうまでもない。ガイドヘルパーの活動によって、視覚障害者の日常生活や社会生活が充実することは疑う余地がない。視覚障害者の生活状況が充実すればするほど、社会の福祉の状況が底上げされることになる。
したがって、たった一人がするガイドヘルパーの活動だとしても、社会全体では大きな力になるのであり、自らの活動は社会の福祉の状態を底上げする大きな力の一端を担っているとの認識をもってもらいたい。
コ.サービスを受ける側の人との関わりを常に忘れないこと
人は道を歩いていて知り合いに出会ったとき、一般的には、挨拶を交わすはずである。ガイドヘルパーが一人で道を歩いているときに、知り合いの視覚障害者が通りかかったならば声をかけるだろうか。積極的に声をかける人もいれば、知らん顔して通り過ぎる人もいるだろう。
仕事として関わっている人同士が、道で出会ったときには、恐らくはどちらからともなく挨拶の声をかけるだろう。しかし、相手が視覚障害者だとなぜ声をかけないのだろうか。ガイドヘルパーとしてだけのかかわり合いにしたいと考えている人もいるだろうし、わざわざ声をかけるだけの付き合いではないと考えているのかもしれない。
道で出会っても声をかけようとしないガイドヘルパーがいたとしても、ガイドヘルパーの仕事をする上では何の支障もないかもしれない。しかし、視覚障害者は前から誰が歩いてきているのかを把握することができない。そのことを認識しながらも、ガイドヘルパーから声をかけようとしないのは、利用者である視覚障害者との信頼関係が密になることを避けているのではないかと考えるのは、深読みしすぎだろうか。いずれにせよ、ガイドヘルパーが利用者との関係を密にする努力に欠けていれば、信頼関係を構築できるとは思われないのである。
3.利用者の苦悩!?
同行援護における外出時の経費の負担問題については、さまざまな意見が飛び交っている。つまり、視覚障害者の外出時において、視覚障害者とガイドヘルパーが交通機関を利用するときのガイドヘルパーの運賃を誰が負担するのか、食堂に入ったときにガイドヘルパーの食事代を誰が負担するのか、映画や娯楽施設の入場料はどうするのか、等々である。
これらについての意見は三つに集約できる。それらは、当然に利用者が負担すべき、当然にそれぞれが自分の分を負担すべき、事前に話し合って負担の方法を決めておくべき、の三つである。3番目の方法が合理的であるかのように思われるかもしれないが、はたしてそのようにいえるだろうか。なぜなら、利用者は弱い立場におかれており、事前に決めるときにガイドヘルパーから「ヘルパーが負担するのであれば、ガイドは引き受けられない」と言われたら、利用者は負担せざるを得なくなるからである。
この負担の問題をどう扱うかは、大きな課題である。
同行援護従業者(ガイドヘルパー)の資格取得において不適格と思われる者に対する扱いをどうするかの問題も、これまた大きな課題である。
(1)費用の負担原則は
同行援護サービスを提供しているある事業所の『通信』に次のようなことが書かれていた。
「サービスをする側と受ける側が対等の関係であることを認識しなければなりません」と。
「共に生きる社会」の実現のためには意義を挟む余地がない意見である。ところが、他の箇所では飲食代におけるヘルパーと利用者との関係について次のように書かれていた。
「飲み会やパーティーなどの場合は当然利用者負担となります。ヘルパーさんに負担させるのはおやめください」。
「原則は適切なお昼の食事代のほかはすべて利用者の負担となります」などと書かれていた。この原則なるものに強く疑問を感じた。私は次のように考えている。
-
-
-
- 同行援護利用時の交通費や入場料等の外出時にかかる必要経費については、利用者が二人分を負担するのは一般的である。
この点には異論はない。なぜなら、近距離の交通費は、視覚障害者一人で利用しても、ガイドヘルパーとともに二人で利用しても原則として同額だからである。また、入場料については、視覚障害者がガイド ヘルパーの同伴を望むのであるから、二人分の費用を負担せざるを得ない状況を承知しているからである。
ただし、長距離の場合にはこの原則が当てはまらないし、非常に高すぎる入場料の場合には二人分の負担は視覚障害者に重くのしかかってくるので、これらについては別の方法を考える必要があると私は考えている。その詳細はここでは割愛する。 - 昼食代以外は「すべて利用者の負担」とする「原則」は誰が決めたのか。この事業所だけの「原則」なら異論は挟まない。なぜなら、それが嫌ならば、この事業所との契約を解除すれば済むからである。しかし、いかにも実施主体である行政が決めた「原則」であるかのような表現は、何の根拠もなく、利用者に負担を強制するものであるといわざるを得ない。
- 飲み会やパーティーにおけるガイドヘルパーの参加費も利用者に負担させる「原則」にはいっそう強く疑問を感じる。ガイドヘルパーは視覚障害者の介助のために参加するのであるから、一般的には参加費を支払う必要はない。ガイドヘルパーが会場で食べたり飲んだりするならば、参加費を支払わなければならない。介助者として参加しているガイドヘルパーは介助に徹するのが仕事であり、食べたり飲んだりする必要はない。お腹が空くというのであれば、パーティーが始まる前に自分のお金で食事をしておけば済むことである。一緒に参加するから一緒に食べたり飲んだりするのが当然だと考えるならば、自分の参加費は自分で支払うべきではないのか。
- 同行援護利用時の交通費や入場料等の外出時にかかる必要経費については、利用者が二人分を負担するのは一般的である。
-
-
利用者にパーティーへの参加費を出してもらい、かつ、同行援護の利用料も利用者からもらうというのは、二重取りといわざるを得ない。ガイドヘルパーは仕事でパーティーに参加するのであるから、参加中は仕事をするべきである。パーティーにはコンパニオンがスタッフとして配置されていることがある。コンパニオンは料理を取り分けたり、飲物をグラスに注いだりしている。それは仕事としてやっているのである。決して食べたり飲んだりはしない。
パーティー参加費は安くはない。障害基礎年金のみで生活している視覚障害者に多額の負担をかける「原則」は、誰が決めたのか。そんな「原則」はすぐに改めるべきである。利用者である視覚障害者の「弱みに付け込んだ」原則といわざるを得ない。
(2)研修の課題
同行援護従業者(ガイドヘルパー)の資格は、研修さえ受講すれば、恐らくは問題なく取得できるのである、と述べておいた。「研修さえ受講すれば」に大きな問題点がある。
同資格取得のための研修受講に際しては、受講者に関する欠格条項はない。すなわち、誰でも研修を受けることができる。それが、たとえ視覚障害者であってもである。
一般的にいって、視覚障害者は同行援護サービスの利用者であるかもしれない。その利用者が研修を受けてガイドヘルパーの資格を取得できるのである。利用者がサービス提供者になることが絶対に問題であると私は考えているのではない。問題点は次のところにある。
同行援護においてもっとも重要なことは、利用者である視覚障害者の安全をガイドヘルパーは確保しなければならないという点である。ガイドヘルパーが絶対に安全確保できるかどうかは断言し得ない。しかし、一定の研修を受けている健常者であるので、安全確保ができると判断されるからこそ、資格が与えられるのである。しかし、周辺の状況を把握することが困難な視覚障害者が、ガイドヘルパーとして利用者の安全を確保できるなどと誰が断言できようか。
以上のことを考えるならば、この研修の受講者を「誰でもいい」などとするのではなく、一定の条件を付けるべきではないだろうか。それは、決して「欠格条項」を容認するようなことではない。利用者である視覚障害者の安全確保を担保するためには必要であると私は考えている。
この問題について、厚生労働省はどのように考えているのだろうか。
「共に築く共生社会の実現へ」パネルディスカッション開催 |
Contact
お問合せ
障がい者の文化芸術活動及び鑑賞に関するご相談・
事業・ホームページ・情報紙に関するお問合せ
072-290-0962
受付時間:平日 10:00~18:00